(お聞きしたのに記憶があいまいで・・)
白地の京友禅の着物で、シミがとれない着物の地色替えをしました。
まずは、替える前の状態を
白地の京友禅・熨斗柄
細い方の着物で、今の標準寸法よりも前巾・後巾が短め。
でも、柄がピッタリ合っていて、仕立て方も内揚げなしの仕立てで、
着る人用に寸法を合わせて柄を描いて作られた着物のようです。
ポイントの柄には駒刺繍がほどこされていて、熨斗柄の無地部分は箔で柄が描かれています。
古典柄で華やか。
残念なことに、白地だから、全体に変色したシミが目立って、このままでは着られません。
それで、地色を黒く染めることにしました。
染め上ってきた反物状態、仕立て前なので、全体はわかりませんが、
部分的に写真を撮って、下手なパソコン処理で柄をつなげてみました。
裾部分のもとの画像
黒地になるとこんな感じ
右後肩から右後袖 もとの画像
黒地になると、こんな感じ
左前胸・衿から左前袖
さて、私は友禅の模様描きですので、染替えしみ抜きのプロではありません。
加賀友禅は金彩や刺繍を使わないため、染替えの時、どの程度箔や刺繍がもつのか、
よくわかりません。
そのことをご了解いただいた上で作業させていただきました。
刺繍部分と箔部分ちょっと柄のアップしますね。
もとの刺繍・箔部分
刺繍があるだけで、立体感が出て豪華ですよね。
先に染め上がりの画像を出して比較しますが、
染め上がりの状態
まず、仕立て上がりの着物を解いて、生地の状態にしました。
作業にかかる前に、一度、生地を水につけてもらい(染屋さんに)、汚れやしわを取ってもらいました。
この時点の写真はありませんが、
刺繍は残っていたものの、刺繍糸がかなり劣化していて、太い金糸を留めていた細い糸がボロボロと切れて、刺繍糸を残すか取ってしまうか微妙でした。
箔は綺麗に残っていました。(箔は水に強い?)
地色の黒を染めてもらい、高温の蒸し そして、余分な染料を落とす水元(水につける)、湯のし(アイロンのようなもので生地のゆがみをなおす)の工程を経て、染め上ったら、
刺繍は、金色が白くなりボロボロと取れ、刺繍糸は全部はずすことにしました。
箔は、水には取れなかったけれど、熱に弱かったかな、ほぼ全部落ちていました。
なので、仕上げに金で輪郭や柄を足し、修正。
刺繍の豪華さ・立体感はなくなりましたが、充分に綺麗な着物に染め変わりました。
黒地は白地と雰囲気が変わって、かっこいい。
ただ今、仕立てに出しています。
おばあさま、お母さまが着た着物をちょっと化粧直しして、今高校生のお嬢さまが着られます。
細くて可愛い方で、時間を経たアンティークな感じは似合いそう。
こんな風に長く大切にされる着物って、「いいなぁ」って思うんです。
(無事、着物の形に生き返ることが出来て、ホッとしているところもありで・・
乱暴な直し方だったらごめんなさい・・)
仕立て上がlりが楽しみです。
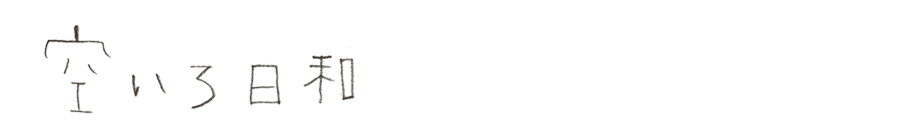









0 件のコメント:
コメントを投稿